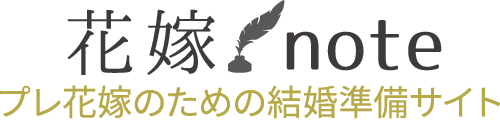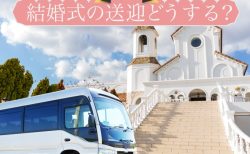新婚夫婦のお金の管理ガイド。家計分担方法とルール

結婚したら夫婦の間で必ず考えなければいけないのは、日常的な家計や将来に向けた貯蓄など、お金の管理に関すること。
家計の管理方法やマネープランに、頭を悩ませる新婚夫婦も多いようです。
困りがちな「夫婦のお金の管理方法」や「お金の話の切り出し方」「賢く家計を管理する方法」について解説します。
新婚生活や結婚式のための計画的な貯金の方法もご案内します。
どちらが管理?夫婦のお金を管理する3つの方法

夫婦のお金を管理する方法は大きく3つあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
働き方や収入の状況などに合わせて、2人に合った方法を選択しましょう。
1.生活費用の共通口座(財布)を作る
毎月決まった額を共通口座に入れて、家計費として管理します。
それぞれが口座に入れる金額は、収入に応じて決めるカップルが多いよう。もちろん5:5の同じ金額で折半する夫婦もいます。
残ったお金は、個人で自由に使えるところが特徴的です。
【メリット】
口座を共有することで2人とも収支を把握できる
【デメリット】
相手の家計以外の収支や、貯蓄状況が分からない
【こんな家庭におすすめ】
共働き、趣味や娯楽費は自分で自由に使いたい
2.費用項目ごとに夫婦で分担する
- 夫→家賃・光熱費・通信費などの固定費
- 妻→食費・雑費などその他の費用
といったかたちで、費用項目ごとに分担して生活費を支払います。
誰がどの項目を負担するかは、収入額に合わせて決めるのが一般的。出産などで収入・支出に変化があれば、その都度話し合って、分担バランスを決めると喧嘩になりにくいでしょう。
なお貯金は別々に貯めることが多いようです。
【メリット】
個人が自由に使えるお金が多い
【デメリット】
インテリアなどグレーゾーンの項目ができやすい
【こんな家庭におすすめ】
共働き、趣味や娯楽費はお互いに自由に使いたい、楽な方法で家計管理したい
3.妻または夫が一括で管理する
夫婦のどちらかがお互いの収入を、一括で管理する方法。
個人が使えるお金は、お小遣い制にするのが一般的です。
【メリット】
お金を一元管理することで、収支や貯蓄の状況が把握しやすい
【デメリット】
管理していない側に収支が不明瞭になりがち
個人で使えるお金が限定される
【こんな家庭におすすめ】
専業主婦(夫)家庭、夫婦のどちらかがお金の管理が得意
【共働き家庭】向いている家計の管理方法

お互いに収入がある共働き家庭は、2人とも家計を負担することが多いので「共通口座で管理する」「項目ごとに分担して管理する」方法が向いています。
なお共働き家庭は、家計分担だけでなく貯金方法にも注意して。
お互いの貯蓄をあてにした結果、必要なときに貯金が無い、ということが起こるかもしれません。
将来的に「何に」「いくら」必要か、ライフプランを話し合い、目的別に一定額ずつ貯蓄に回すなどの工夫が必要です。
夫婦円満のポイント:生活費の負担割合
基本的に共働き家庭では、2人とも家計を負担するので、不平等感を作らないことが大切です。
一番無難なのは、収入の割合によって家計負担額を決める方法。これなら夫婦で家計を折半するのに比べて、収入が少ない方の負担が重くなりすぎません。
項目別に家計を分担するなら、担当項目を調整して、お互い納得できる負担バランスにしましょう。
【専業主婦(夫)家庭】向いている家計の管理方法

片方が仕事をしていない専業主婦(夫)家庭は、日常の買い物や支払いを担当している方が、家計を一括管理するとスムーズですし、やりくりも楽です。
家計簿をつけるなどして、家計を管理していない方も収支に納得できるよう対策しましょう。
夫婦円満のポイント:生活費とお小遣いの分け方
家計を一括で管理することが多い専業主婦(夫)家庭では、生活費とお小遣いをどのように分けるかが、家計をうまく回すポイント。
■家計を管理している方もお小遣いを設定する
お小遣いを設定しないと、家計費と個人の支出が曖昧になり、家計の支出が大きくなってしまいがち。
きちんとお小遣いを決めることで、出費にメリハリをつけましょう。
■働いている側から不満が出ないお小遣い額を設定する
支出を切り詰めたいあまり、働いている夫や妻のお小遣いを減らしすぎると、「収入を得ているのは自分なのに…」と不満が生まれるかもしれません。
お小遣いの額は、給料の1~2割が目安と言われています。
給料の額を根拠に適正な金額を決めるのがおすすめ。
結婚前にするべき、お金の話と夫婦のルール

結婚生活では、お金の管理や貯蓄がとても重要です。結婚後の世帯収入や支出額の見込みを知るために、
- 今の収入、支出、貯金額
- ローンや奨学金の返済額
といった現在の金銭状況は、早めにオープンにしておきましょう。
ライフプランと、それに合わせた資金計画を作る
「マイホームがほしい」「子供は3人ほしい」といった今後の人生設計によって、支出額は大きく変わります。
まずは2人のライフプランを共有して、いつごろどんなお金が必要になるか見通しを立てましょう。
そのうえで、きちんと考え方を擦り合わせてルールを作っておくべき項目があります。
- 家計の管理方法
- 結婚後の月々の貯蓄額や目標額
- お互いが自由に使える額
- 今後の働き方
- 産休・育休時の家計負担
話し合いのタイミングや切り出し方
夫婦のお金に関する話し合いは、結婚前(一緒に住み始める前)に終えておくのがベター。
ルールを決めないまま結婚生活を始めると、「とりあえず」のやり方で家計管理することになりがち。
貯金が貯まらなかったり、家計の負担について不満を感じたりするリスクがあります。
とはいえ、お金の話はなかなかストレートに切り出しにくいもの。
まずは結婚式や新婚生活の話題を出しましょう。そこで演出やインテリアなどの話題を出せば、自然と費用の話になりますから、違和感なく結婚後の家計管理について話し合えます。
また実際の生活を細かくイメージしながら話をすれば、より現実的で具体的な話がしやすくなりますよ。
新婚夫婦向け、賢く家計管理する3つのアイデア

賢い家計の管理の仕方には、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、代表的な3つの方法をピックアップしてご紹介します。
1:家計簿をつける(お金の流れを見える化)
家計簿をつけると、家庭全体のお金の流れを把握しやすくなります。
何にいくら使っているかが分かれば、削れる支出も分かりやすくなり、節約も成功しやすいです。
2:家計管理用のアプリを共有する
家計管理には、スマホやパソコンから使えるアプリが便利です。夫婦で共有すれば、それぞれが常に最新の家計を把握できます。
金融機関と連携していて貯蓄額がリアルタイムで確認できるものや、利用額をグラフ化してくれるもの、レシートの写真から数字を読み取れるものなど、機能性にすぐれたアプリがたくさんあります。
人気が高い家計管理用アプリを3つご紹介します。
●Zaim 公式サイト Android版 iOS版
スマホカメラで、レシートの読み取りが可能。
銀行やクレジットカードと連携させて、出入金の管理もできます。
さらに、予算残高の管理や、家計簿をグラフで分析する機能付き。
家計簿を家族で共有できるので、お金の流れを夫婦でしっかり把握したいという家庭にもおすすめ。
●マネーフォワード Android版 iOS版
データ連携できる金融機関が多いのが強みの家計管理アプリ。
自動家計簿作成や入出金管理、レシート読み取りなどの機能が使えます。
条件が近い人の平均データをもとにした家計診断もできるので、節約や貯金を効率化したい夫婦にぴったり。
●らくな家計簿 Android版 iOS版
エクセルへのデータの送り出しと、インポートができる家計簿アプリ。
面倒な複式簿記にも対応しています。
また、音声入力ができるので、細かい作業もらく。
月始め日の設定機能で、給与の入金サイクルに合わせた管理もできます。
3:用途別に共通口座を複数用意する
「生活費」「余暇・予備費」「貯蓄」など、項目別に共通口座を用意して、家計を管理します。
項目ごとに使える金額が決まっているので、使い込みの心配がありません。無駄遣いした箇所や節約できる箇所を見つけやすい方法でもあります。
「生活費」「余暇・予備費」の支出が残高の範囲内に収まるようようにやりくりして、「貯蓄」口座には基本的に手をつけないのが基本ルール。
新婚生活・結婚式に必要な費用の内訳

新婚生活の準備や結婚式には、漠然と、お金がかかりそうだな…というイメージを抱いているカップルも多いはず。
内訳は後ほど解説しますが、結婚を決めてから新婚生活のスタートまでに、トータルで平均500万円以上もの費用が必要になります。
現在の貯金額から逆算して、どれくらいの金額を貯めればいいかを、早めに確認しておきましょう。
新婚生活費用
新婚生活実態調査2018(リクルートブライダル総研調べ)の結果によると、新婚生活のために、インテリアや家具、家電を購入したカップルは約7割。
平均金額は次のとおりです。
- インテリア・家具:28.4万円
- 家電製品:33.4万円
結婚式費用
また、ゼクシィ 結婚トレンド調査2020調べによると、結納から新婚旅行までにかかった費用の平均額は469.2万円。
内訳は次のとおりです。
- 結納:22.7万円
- 両家顔合わせ:6.5万円
- 婚約指輪:35.7万円
- 結婚指輪:25.1万円
- 挙式・披露宴:362.3万円
- 新婚旅行:65.1万円
- 新婚旅行土産:11.6万円
なお挙式・披露宴費用はご祝儀や親の援助でまかなえる場合もあります。同調査によると、ご祝儀の総額は平均227.8万円、親の援助は平均172.1万円です。
新婚生活・結婚式費用を、上手に貯金管理するコツ

2人で計画的に貯金・管理するには、いくつかコツがあります。
自動振込サービスで貯金用口座に振り込みをする
あらかじめ貯金するお金を、自動振込サービスを使って貯蓄用口座に貯めてしまいます。この方法なら、手間なく確実に貯金できますよ。
入金額は、目標貯金額やそれぞれの収入額などに合わせて決めましょう。
振込先は普通預金の共通口座でもOKですが、会社の財形貯蓄制度や積立預金を使うのもアリ。
財形貯蓄制度とは、給料から一定額が自動的に貯蓄口座へ積み立てられる制度です。一部、利子などに非課税優遇措置があります。
積立預金は、設定した金額が自動的に積み立て口座に引き落とされる仕組み。定期預金の一種なので、たいていの銀行は普通預金よりも高い金利を設定しています。
毎月の収支をチェックする
毎月の収支をチェックすれば、無駄遣いしているポイントや節約できるポイントが見つかります。
なお食費といった毎月変動する項目より、家賃や通信費といった固定費を削減するほうが、トータルで節約できる金額が大きくなりやすいです。
まとめ:夫婦になるならお金の管理方法もきちんと話し合うべき!
- 夫婦のお金の管理方法は大きく「共通口座で共同管理」「項目ごとに分担」「一方が一括管理」の3つ
- 共働きか専業主婦家庭かで適した管理方法が違う
- 結婚前にお互いの収支の状況を共有し、家計の管理や将来的なマネープランの話し合いをするべき
- 結婚前には新婚生活や結婚式のための貯金をすることも必要
- 家計簿や家計管理アプリ、項目別の共通口座などを活用して賢く家計管理を
ライフプランを共有する夫婦にとって、お金の使い方はとても大切なこと。
ふたりに合った管理方法で、賢く支出をコントロールしましょう!